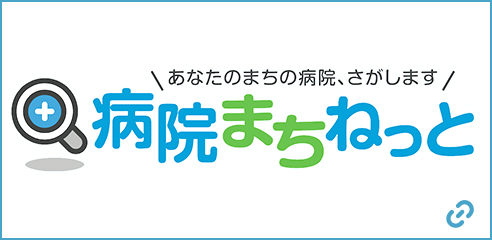- HOME>
- 滲出性中耳炎

滲出性中耳炎は、中耳(鼓膜の内側の空間)に粘り気のある液体(滲出液)が溜まる病気です。
通常、中耳は空気で満たされていますが、何らかの理由で耳管(中耳と鼻の奥をつなぐ管)の働きが悪くなると、液体が溜まって聴こえに影響が出てしまいます。
この病気の主な症状は、「聞こえにくさ」です。
会話が聞き取りにくい、テレビの音量を大きくする、「ん?」と聞き返すことが増えるなどの変化に気づくことがあります。
また、「耳が詰まった感じ」や「水の中にいるような感じ」がする、自分の声が響いて聞こえるといった症状も現れます。
痛みはほとんどないため、特に小さなお子さんの場合は、本人が訴えないと気づきにくいことが特徴です。
日本耳鼻咽喉科学会の調査によると、3〜6歳の幼児の約20%が一度は滲出性中耳炎を経験するとされています。
特に保育園や幼稚園に通い始めた時期に発症しやすく、注意が必要です。
滲出性中耳炎の主な原因としては、風邪やアレルギー性鼻炎による鼻の炎症が耳管に広がることが挙げられます。
鼻水やのどの炎症によって耳管が詰まったり、うまく開かなくなったりすると、中耳の換気がうまくいかず、液体が溜まりやすくなります。
また、アデノイド(のどの奥の扁桃腺のような組織)が大きくなって耳管を圧迫することも原因になります。
小さなお子さんは耳管が短く水平に近いため、大人よりも滲出性中耳炎になりやすい体の構造をしています。
滲出性中耳炎を放置するリスク
「痛みがないから」「そのうち治るだろう」と放置してしまいがちな滲出性中耳炎ですが、適切な治療を受けないと様々なリスクがあります。
最も重要なのは、特に発達段階のお子さんへの影響です。
言葉を覚える大切な時期に聴こえが悪いと、言葉の発達の遅れや発音の問題につながる可能性があります。
また、学校では先生の話が聞き取りにくくなり、学習に影響することもあります。
さらに、液体が溜まった状態が続くと、中耳内に癒着が起こり、鼓膜や耳小骨(音を伝える小さな骨)の働きが悪くなる「癒着性中耳炎」に進行することもあります。
この状態になると治療が難しくなり、永続的な聴力低下を引き起こす可能性があります。
滲出性中耳炎の診断方法
① 問診
症状の経過や風邪の有無、アレルギーの状態などを詳しくお聞きします。
特にお子さんの場合は、保護者の方が気づいた行動の変化(テレビの音量を上げる、聞き返しが増えたなど)が重要な手がかりになります。
② 耳鏡検査
専用の器具で鼓膜の状態を観察します。
滲出性中耳炎では、鼓膜の色や光の反射が変わり、中の液体が透けて見えることもあります。
③ ティンパノメトリー
中耳の圧力と鼓膜の動きを測定する検査で、痛みはなく短時間で終わります。
必要に応じて「純音聴力検査」も行い、聴力低下の程度を調べます。
これらの検査結果を総合的に判断し、最適な治療方針を決定します。
滲出性中耳炎の治療方法と経過
滲出性中耳炎の治療は、原因や症状の程度によって異なりますが、基本的には以下の方法があります。
薬物療法
鼻の炎症やアレルギーが原因の場合は、それらを改善する薬を処方します。
抗ヒスタミン薬や鼻炎用の薬、場合によっては抗生物質などを使用します。
また、耳管の機能を改善するための薬も有効です。
耳管通気療法
専用の機器を使った「耳管通気療法」を行います。
これは鼻から中耳に空気を送り込み、耳管の働きを改善して、溜まった液体を排出しやすくする治療法です。
痛みはほとんどなく、即効性があるのが特徴です。
小さなお子さんでも怖がらずに受けられるよう、スタッフが丁寧にサポートします。
チューブ治療(鼓膜換気チューブ留置術)
薬物療法や耳管通気療法で改善しない場合や、症状が重い場合には、鼓膜に小さな穴をあけて換気チューブを入れる治療を行うことがあります。
このチューブにより、中耳の換気が改善され、液体が排出されやすくなります。
日帰り手術で行うことができ、多くの場合6か月〜1年程度でチューブは自然に抜け落ちます。
小さなお子さまでは、全身麻酔が必要となることがあり連携医療機関をご紹介いたします。
治療を始めると、多くの場合2〜4週間程度で症状の改善が見られます。
ただし、再発しやすい病気なので、治療後も定期的な経過観察が重要です。
当院では、治療後の聴力回復の状態を確認するためのフォローアップ検査も行っていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ

滲出性中耳炎は、適切な治療を受ければ多くの場合改善する病気です。
しかし、特にお子さんの場合、本人が症状を訴えられないことも多く、保護者や周囲の大人が変化に気づいてあげることが重要です。
当院では、最新の診断機器と専門知識を活かし、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療をご提案します。
聴こえの問題は言語発達や学習にも影響するため、心配な症状があれば早めに姫路市飾磨区のうおずみ耳鼻咽喉科までご相談ください。