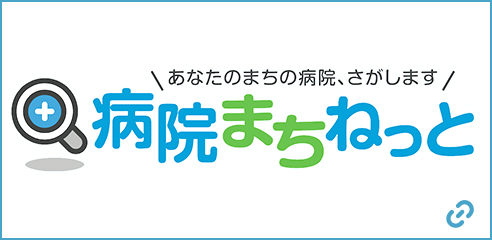- HOME>
- 難聴

難聴とは、音が聞こえにくくなる状態のことです。「耳が遠い」「耳が悪い」などとも表現されます。
日本では約1,400万人(9人に1人)が難聴に悩んでいると言われており、特に高齢者では3人に1人が難聴を抱えているという調査結果もあります(日本耳鼻咽喉科学会, 2019)。
主な症状
- 会話が聞き取りにくい
- 「え?」「何?」と聞き返すことが増える
- テレビやラジオの音量を大きくする
- 電話での会話が難しい
- 周囲から「声が大きい」と言われる
難聴の種類
伝音難聴
外耳や中耳の問題で、音を内耳に伝える経路に障害がある状態です。耳垢栓塞、中耳炎、耳小骨の異常などが原因となります。
感音難聴
内耳(蝸牛)や聴神経の障害によるもので、加齢、騒音、薬の副作用、突発性難聴などが原因です。
混合性難聴
伝音難聴と感音難聴が合わさった状態です。
また発症時期によって「先天性難聴」(生まれつきの難聴)と「後天性難聴」(生後に発症する難聴)に分けられます。
特に子どもの難聴は言語発達に大きく影響するため、早期発見・早期療育が非常に重要です。
主な原因

最も一般的な原因は「加齢性難聴」です。年齢とともに内耳の細胞が徐々に減少し、特に高い音から聞こえにくくなります。
厚生労働省の調査によると、65歳以上の約40%、75歳以上では約70%が加齢性難聴を抱えていると報告されています。
また、大きな音に長時間さらされることによる「騒音性難聴」も増加傾向にあります。
工場や建設現場などの職業性騒音だけでなく、イヤホンで大音量の音楽を長時間聴き続けることでも発症するリスクがあります。特に若い世代での予防が重要です。
その他、中耳炎などの耳の病気、突発性難聴、メニエール病、聴神経腫瘍などの疾患、特定の薬剤(抗生物質、抗がん剤など)の副作用、頭部外傷、全身疾患(糖尿病、高血圧など)も難聴の原因になることがあります。
遺伝的要因も重要で、先天性難聴の約60%には遺伝子変異が関与しているとされています。
また、家族に難聴者がいる場合、難聴のリスクが高まることが知られています。
難聴とうつ病・認知症の関係
難聴を放置すると、コミュニケーションの困難さから社会的孤立を招きやすくなります。
家族や友人との会話が減り、外出を避けるようになると、孤独感や抑うつ症状を引き起こすリスクが高まります。
実際、難聴がある高齢者はない高齢者と比べて、うつ病のリスクが約2.5倍高いという研究結果もあります(米国ジョンズ・ホプキンス大学, 2018)。
さらに近年、難聴と認知症の関連が注目されています。
難聴が中等度以上ある高齢者は、難聴のない方と比べて認知症の発症リスクが2〜5倍高まるという複数の研究結果が報告されています。
これは、聴覚からの情報が減ることで脳への刺激が減少することや、聞き取りの努力による認知的負荷の増大などが関係していると考えられています。
子どもの場合、難聴を早期に発見・対応しないと、言語発達の遅れ、学習困難、社会的発達の問題につながる可能性があります。
特に言語獲得の重要な時期(0〜3歳頃)の聴覚は非常に重要です。
こうしたリスクを考えると、難聴の早期発見と適切な対応が非常に重要であることがわかります。
補聴器や人工内耳などの聴覚補助機器の使用、コミュニケーション方法の工夫、必要に応じた治療などにより、難聴による生活の質の低下を最小限に抑えることができます。
当院で行う検査
純音聴力検査
防音室で、様々な周波数(高さ)と音の大きさの音を聞いていただき、どの程度の大きさから聞こえるかを測定します。
これにより、難聴の程度や特徴(どの周波数が聞こえにくいか)を詳細に評価できます。
語音聴力検査
数字や単語、文章などを聞いて、どれだけ正確に聞き取れるかを調べる検査です。
実際のコミュニケーション能力を評価する上で重要です。
ティンパノメトリー
中耳の状態や機能を調べる検査で、伝音難聴の診断に役立ちます。
難聴の治療法
原因疾患の治療
耳垢栓塞や中耳炎など、治療可能な原因がある場合は、まずその治療を行います。
耳垢除去、薬物療法、必要に応じて手術的治療などを行うことで、聴力が改善する可能性があります。
薬物療法
突発性難聴やメニエール病などでは、ステロイド薬や循環改善薬などの内服薬や点滴治療が有効なことがあります。
特に突発性難聴は発症から早期(できれば1週間以内)の治療開始が重要で、治療が遅れるほど回復率が低下します。
補聴器
感音難聴や治療で改善しない伝音難聴では、補聴器の使用が基本的な対応方法となります。
現代の補聴器は小型化・高性能化が進み、デジタル技術により騒がしい環境でも会話が聞き取りやすくなるなど、様々な機能が搭載されています。
人工内耳
高度〜重度の感音難聴で、補聴器の効果が限られる場合は、人工内耳が選択肢となることがあります。
人工内耳は内耳の機能を電気的に代替する装置で、特に先天性難聴のお子さんや、成人になってから高度難聴になった方に効果を発揮します。
まとめ
姫路市飾磨区のうおずみ耳鼻咽喉科では、補聴器相談医・騒音性難聴担当医の資格を持つ院長が難聴の診療や補聴器装用の相談を行っています。
ご自身やご家族の聴こえに少しでもご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。